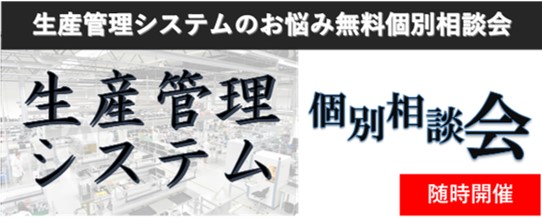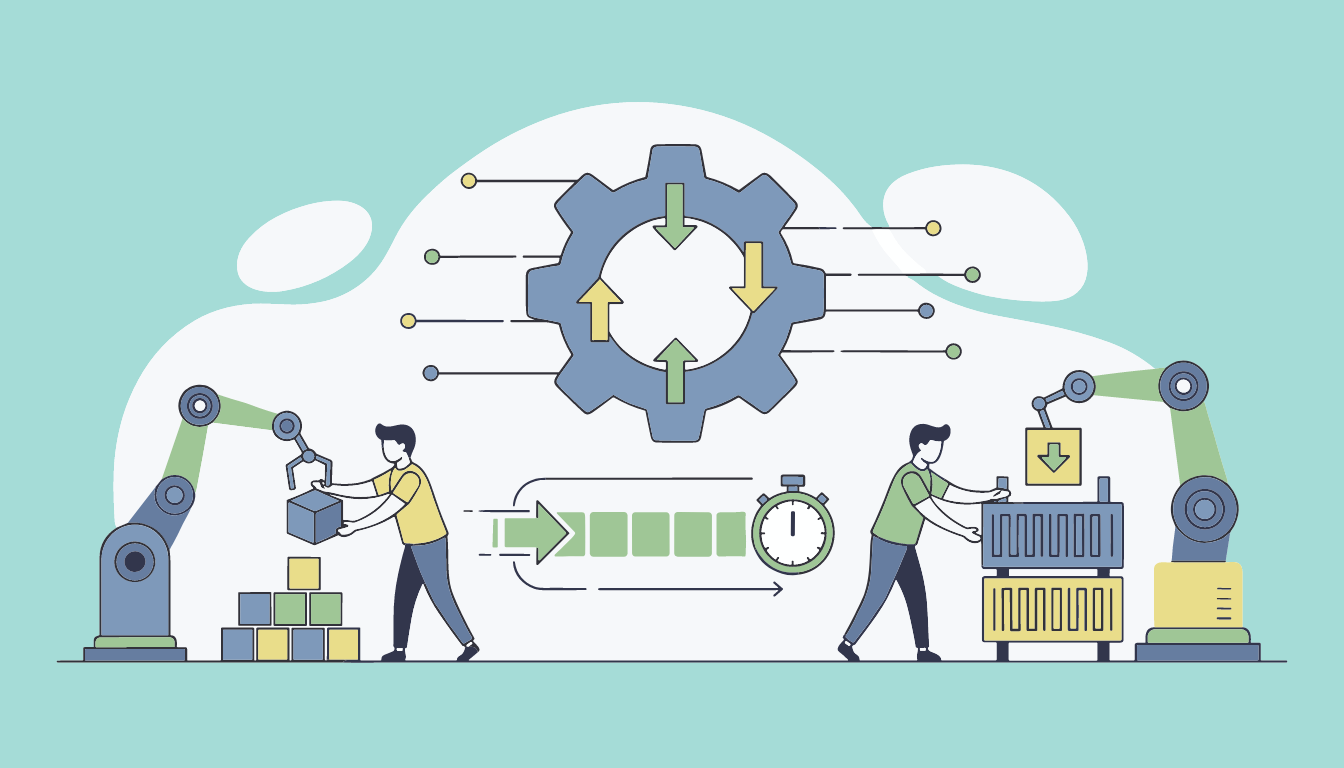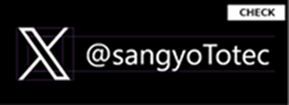自動計画立案時の注意点について〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜

連載テーマ「生産スケジューラ(生産計画システム)導入で
失敗しないための8つのポイント」
- Vol.1 生産スケジューラ(生産計画システム)導入の目的とは
- Vol.2 スコープの明確化とは〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜
- Vol.3 生産スケジューラを使った現状の業務運用・管理手法からの脱却
- Vol.4 プロジェクト推進体制の重要性について〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜
- Vol.5 自動計画立案時の注意点について〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜
- Vol.6 プロトタイプ評価方法の注意点について〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜
- Vol.7 生産スケジューラ(生産計画システム)導入支援パートナー選定時の6つのポイント
- Vol.8 生産スケジューラ導入で成功するためのポイント〜生産スケジューラ(生産計画システム)導入で失敗しないために〜
前回は「プロジェクト推進体制の重要性」について説明しましたが、今回は「自動計画と計画手調整の切り分け」について説明します。
上記判断は時に非常に難しいことがあり、この判断によってプロジェクトのスケジュール遅延や運用停止になるケースも存在しますので注意が必要です。
生産スケジューラ(生産計画システム)に関する資料をダウンロードできます
各種要件への対応方法について
現状の計画方法や希望する計画方法を元に、生産スケジューラに求める要件をまずは整理します。その後各要件に対してどのように対応するのかを検討していきます。
検討する中でまず3つの分類分けを行います。
①パッケージ標準機能で対応
②追加プログラムの開発で対応(標準機能では対応不可な要件)
③システム対応は行わず、運用業務で対応
そして①とした中でも、更に切り分けが必要となります。
- 自動計画ロジックに組み込み対応する
- 自動計画後の計画結果情報を確認し、人が計画を手調整して対応する
自動計画と計画手調整の切り分けについての注意点
1.自動計画とするケース
【要件例:現状計画で金型の数量を考慮した計画を行っている】
- 現状計画で考慮している
- 標準機能で対応できる
- 頻度も多い
- 対応するためのマスタ整備は可能である
上記のような要件は自動計画ロジックに組み込み、自動計画の精度向上に向けて対応を行っていきます。
2.計画手調整とするケース
【要件例:特殊品目Zの時は***を考慮して計画している】
とした要件があった場合に、自動計画ロジックへの組み込み方法を検討する前に、その頻度をお聞きします。
それが週に何回も発生するケースであれば対応に向けた実装を行いますが、発生頻度が年に数回程度のイレギュラー要件が発生することがあります。
そういった場合はロジックに組み込むことが可能だとしても、そのためにマスタを用意しロジックを複雑化するよりは、そのタイミングのみ計画を手調整した方が良いと推奨します。
計画要件を洗い出した後は、頻度についても確認しましょう。
【要件例:品目Aと品目Hは連続して製造できない】
ロジック対応として品目Aと品目Hが連続して計画されないように計画順を考慮して対応したとします。
そうすることで自動計画した結果、品目AとHが連続して計画されることはほぼ無くなりました。
それであればNG計画発生時にアラートする機能のみを実装し、アラート発生時に計画を手調整して対応して頂くとすることが多いです。
自動計画ロジックで考慮しつつ、仮に発生した場合は計画を手調整して頂くケースとなります。
3.計画ロジックで考慮しないケース
【要件例:製造は設備、段取りは作業員が行っている。段取り内容は品種群ごとに異なり、作業を行える作業員と行えない作業員がいる。(スキルマップ制約)】
製造品目ごとに製造可能な設備をマスタ化して対応します。そして、段取り作業員ごとにスキルマップ(どの設備、どの段取りは可能など)をマスタ化し、作業員ごとに勤務シフトを登録することで、制約とすることは可能です。
しかし、人単位のマスタとなると日々のシフト設定やスキルマップを随時整備することが非常に煩雑となります。
段取り作業員があまりネックになることが無いのであれば、製造可能な設備のみを制約とし、作業員制約は考慮しないとした方が良いです。
もし、高難易度の段取りに限っては人数不足になることがあるのであれば、高難易度の段取りを行える作業員人数のみ(人単位ではなくグループ)を制約とすることで対応すれば良いでしょう。
まとめ
計画で考慮している、考慮すべき、考慮したい内容を全てマスタやロジックに落とし込むことこそが成功への道筋とは言えません。
自動計画で対応するケースと計画手調整で対応するケースを適切に判断し、計画の標準化を行いつつ継続運用が可能な変化に強いスケジューラを構築しましょう。
標準的に自動計画結果の精度は60~80%程度を目標とします。
自動計画で100%の計画結果を望む場合、イレギュラーケースにもマスタとロジックで対応する必要があり、システムが複雑となりすぎるため推奨しません。
※よくある問題
- マスタ設定難易度が高いためマスタ登録者の作業が属人化する
- マスタメンテナンス作業に時間を要する
- マスタとロジックが複雑なため、計画結果の妥当性判断が難しい
- 受注変動、設備増強、品種追加などによりシステムの改修が必要となる
- 結果的に計画精度が低くなり、現場での判断が必要となる。
筆者
プロフィール
山原 研佑 Kensuke Yamahara
経歴:
入社以来生産管理業務のスクラッチ開発を経て、生産スケジューラ(asprova)に携わり約10年。
20サイト以上の導入経験があり、現在は生産スケジューラ(asprova)専任グループのリーダとして活躍中。
提案活動や、導入プロジェクトの責任者としてレビューを担う傍ら、SEの育成に力を入れている。
書籍:Asprova解体新書~生産スケジューラ使いこなし再入門~(高橋邦芳様著/日刊工業新聞社出版) の主役:山原正夫(仮名)という役名で出演。※人物像とは異なります 趣味は、サッカー(現在地域のチームに所属)、フットサル、海外サッカーの観戦 高校時代にテニスで全国大会出場の経験もあり、スポーツ全般を得意とする。
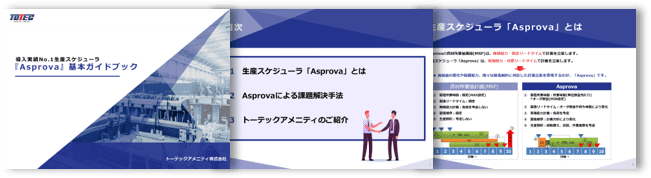
生産スケジューラ『Asprova』
基本ガイドブック
お困りごとがありましたら、お気軽にお問合せください。