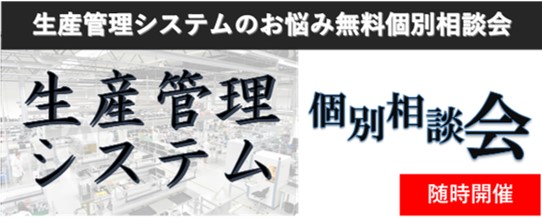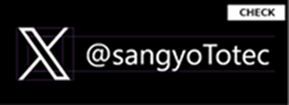マスタの重要性について

連載テーマ「生産管理システム導入を成功に導くポイント」
システムを立ち上げる為に重要な要素の一つがマスタです。既に現行システムで整備されているマスタであれば単純なデータ移行で対応できますが、課題となっている要因がマスタにある場合が多く、新システム立ち上げの壁となっています。 マスタの重要性を考え、整備する上での注意点を見ていきましょう。

生産管理システムを導入を成功に導くポイントはコチラから
生産管理システム導入の際に気を付けたいポイントやマスタの重要性などを解説しています。是非、貴社のシステム導入の際にお役立てください。
そもそもマスタは必要なのか?
なぜマスタが必要なのか。予め決められた設定値に基づいて発注/生産指示を行う為にマスタは必要なものとなります。 例えば品番マスタであれば、
- 品名/標準発注先(製造部署)/保管場所/ロットサイズなどの基本情報
- 製造リード日数
- 安全在庫数
など予め設定しておく事によって、品番と数量/納期さえ指定すれば誰でも指示書/注文書が発行できるようになります。
所要量計算などにより業務を自動化するのであればマスタは必須となります。
業務の簡素化だけではなく、間違った指示を出さないようにする事がマスタの重要な役割となります。
場合によってはマスタ化できないものもあります。
今回だけしか発注しない物(仕様)や取引先の場合はマスタ化するメリットがありません。
あまり勧める事は出来ませんが、マスタが無くてもシステムを稼働させる事はできます。
重要なのは、なぜマスタが必要なのか理解し整備/ルール決めを行う事です。
最初から完璧なマスタは作成できない
前述した通り、ある程度マスタの整備が進んでいるのであれば問題は無いのですが、マスタの整備が進んでいない状況から理想とするところまで一気に進める。というのは無理なケースが多い事を認識する必要があります。
第2回でステップを踏んだシステム導入について提案しましたが、マスタ整備においてもその粒度を最初は粗く、できるところから細かく整備していく事が成功に導くポイントとなります。
第2回の「所要量計算による原材料発注業務の自動化」導入ステップを例にすると
ステップ1:製品在庫管理の徹底
自動化を行う為には原材料の標準発注先、単価、ロットサイズ、発注リード日数、発注点などの原材料マスタだけでなく、どの製品にどの原材料がいくつ使用しているのか、製品の生産計画は正しいのか、また原材料の発注リード日数を加味した計画立案ができるのか、など自動化を行う為の前提条件を揃えるだけでも時間がかかると思われます。
もし製品の生産指示や在庫管理も目的の1つなのであれば、まずは製品にターゲットを絞ってマスタ整備を行う事で製品在庫管理を実現するところから始める事ができます。
また、在庫管理の目的、実践方法についてはこちらの資料で解説しております
ステップ2:原材料の在庫管理の徹底
製品の生産計画や在庫管理が実現できたところで、次へのステップアップとして原材料在庫管理の実現を目指してみる。
このステップで必要なBOM(1製品に対して使用する原材料と使用量を管理するマスタ)を整備し、最終目的の準備を着実に進める。
ステップ3:原材料発注業務の自動化
最後に原材料の発注に関する各種マスタを整備し最終目的達成を目指す。 といった整備するマスタの対象を絞りステップを設ける事を検討してみて下さい。
マスタの運用に関する注意点
マスタが間違っていると誤発注などを招く元となってしまいます。
誰でもマスタが整備できる状況というのは大変危険です。
マスタを変更できる権限設定、変更時には承認を得てから反映するなど、マスタ登録に対するルールを決めて間違ったマスタが登録されないよう管理していく事が重要です。
またマスタは一度登録したら完了ではなく、日々状況に応じて見直す事が重要です。
まとめ
新システム導入において「マスタ整備の遅れ」が要因で遅れているという話はよく聞きます。
かといって不完全なマスタでは使えないシステムになってしまいます。
現時点でどこまでマスタが整備できるのか、目的を達成するためにはどのようなマスタが必要でどのくらいの作業が発生するのかを洗い出し、ここで紹介させて頂いた事例を参考に状況によってはステップを設けるなど確実に進める方法を検討していただければと思います。
マスタについての詳細につきましては、以下のブログでも紹介されています。
生産管理の基準情報(マスターデータ)の整備と維持~基準情報は会社のノウハウそのもの~
筆者
プロフィール
市山 角真 Kadoma Ichiyama
経歴:
これまでに20社を超える製造業のお客様へ生産管理システムを導入。パッケージ導入だけではなく、業種特有の要件に応じたアドオンシステムの開発経験も豊富である。
過去の導入事例では、ハンディ/タブレットを活用した現場システムやWebEDIによる調達業務効率化、また、海外の関連子会社へのシステム展開の実績あり。
TPiCS導入指導者、認定指導員資格を保有
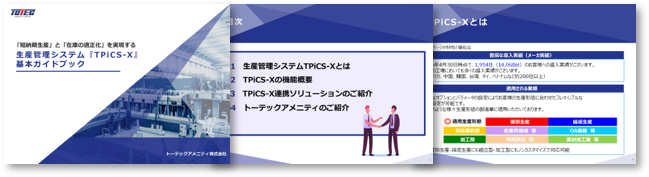
生産管理システム『TPiCS-X』
基本ガイドブック
お困りごとがありましたら、お気軽にお問合せください。