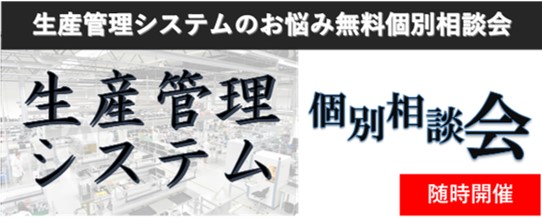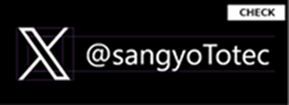資材発注・外注管理 ~社外への手配管理の内容と重点管理ポイントについて~

連載テーマ「生産管理システムを理解する」
- Vol.1 生産管理業務とは〜目的から基本原則まで〜
- Vol.2 生産管理システム~その機能、役割とは?どう選べばよいのか?~
- Vol.3 生産管理の基準情報(マスターデータ)の整備と維持~基準情報は会社のノウハウそのもの~
- Vol.4 生産計画と日程管理 ~生産管理システムにおける生産計画や日程計画の立案とは~
- Vol.5 在庫管理システムと生産管理 ~在庫管理の考え方と実践~
- Vol.6 資材発注・外注管理 ~社外への手配管理の内容と重点管理ポイントについて~
- Vol.7 製造管理~社内における作業管理と工場の統制~
- Vol.8 品質管理~生産管理システムと品質管理の関係~
- Vol.9 生産管理と受注出荷の連携 ~営業活動と工場との関係~
- Vol.10 工場の原価管理~原価低減のための仕組みづくり~
企業の生産活動において1社完結というのは稀で、大抵は仕入先や外注など他企業と付き合いながら業務を遂行していくものです。
今回は、生産管理における発注管理のポイントについて解説します。
発注
一般的な生産管理システムでは、部品や材料のそれぞれに対して標準発注先と標準単価をマスター情報として登録しておき、MRP計算や手入力等で発注データができると、何も指定しなければマスターの情報に従ってどこへいくらで発注するかを自動的に決定します。
パッケージソフトの場合、複数の発注条件をあらかじめ登録しておくとその時の発注量や単価変動などに応じて自動的に複数社のなかから発注先を選定してくれることもあります。
発注行為は基本的に紙面で行われます。すなわち注文書です。
生産管理システムが導入されていれば、発注データにもとづいて注文書が発行されます。
注文書を発行したことでシステムは「発注した」と認識し、発注残として扱います。
紙面以外では電子帳票やEDIによる発注が考えられますが、一部の業界標準手順を除いてカスタマイズやアドオンで機能を補完することが多いです。
受入れ、検収管理
発注した物品が納入されると受入と検収を行いますが、ここで重要なのが、納品物がどの発注によるものなのかが分かることが必要、ということです。
通常、注文書には注文番号が一意で振られます。
納品時はモノと注文内容を照らし合わせて確認する必要がありますから、注文番号が分からないといけない、というわけです。
一番よいのは注文書と納品書をセットで送り、納品時はその納品書をつけてもらうことです。
稀に、仕入先が独自の納品書しかつけられないということもありますので、システム導入前に同意を取り付ける必要があります。
また、受入や検収はシステムに実績データをインプットしなければなりませんが、今日ではソースマーキング(バーコードがついている)が進んでいるため、バーコードを読み取ることで受入や検収の入力を効率化できる可能性があります。
実績データは迅速かつ正確に入力することが望ましいため、システム導入時にあわせて検討したい機能です。

納期管理
発注担当者にとって、発注したから安心というわけではなく納入されるまでが大変な仕事なんだと感じます。
SEとしてお客様にヒアリングすると、よく聞かれるのが「納期遅れをシステムでアラームできませんか」という要望です。
普段から納期確認に追い回されているのでしょう。
しかしお気の毒ですが納期遅れはシステムアラームの対象にはできません。
システムは納期が「遅れた」ことは分かりますが「遅れそう」かどうかは分からないのです。
アラームが出るのは納期の翌日です。
納期管理はシステム化の問題ではなく、4.で述べますが仕入先との取り決めの中で解決すべき課題です。
また、回答納期をもらうという方法もありますが、回答納期をシステムが計算した納期に上書きすることはやめるべきです。
システム上の納期を書き換えてしまうと、回答納期を正として次回のMRP計算がなされてしまいます。
回答納期が繰り上がっているのならまだいいですが、計算納期より後ろの日付だと計算上間に合いませんので結局元の納期で追加発注が出てしまいます。
もし仕入先から出荷情報を先行で入手できれば、納期管理の問題と受入れの効率化がまとめて解決できます。
出荷情報が先行で来ることにより納期遅れが事前に把握できますし、出荷情報をデータとして使えば受入れでの照合や在庫への登録が簡単にできるようになります。
購買先の管理統制
歴史や文化も違う他社企業を自社の都合に合わせてコントロールするのは難しいことです。
購買担当の悩みとしてはおおむね以下の2つに集約されると思います。
「できるだけ安く買うにはどうしたらよいか」
「仕入先が納期を守ってくれない」
これらはシステムで解決する課題ではなく、管理運用面で解決すべき課題です。

できるだけ安く買うにはどうしたらよいか
まず、安く買うための対策としては集中購買と複数社購買があります。
集中購買は、各部署がバラバラに発注するのではなく購買部門などが取りまとめて一括発注するということでボリュームディスカウントを受けやすくする効果があります。
複数社購買は、同じ品目でも購買先を複数社確保しておき、その時々の最も安値の購入先を選択する方法です。
仕入先の立場からすれば競合がいることで競争意識が働き、値下げを申し出るかもしれません。
また複数社から調達できることで災害時などのリスクヘッジにもなります。
仕入先が納期を守ってくれない
さて、納期を守ってもらうには、とにもかくにもまずは仕入れ先との話し合いしかありません。
なぜなぜを繰り返し、納期遅れが発生する原因を共に共有し解決策を考えるしかないのです。
どうしても納期が延びてしまうなら、システムのリードタイム設定を延ばすかバッファ在庫を確保する等マスターの見直しで対応します。
もしこちらが内示やフォーキャストを開示できるのであればそれを仕入先へ提供するというのも有効な手段でこれは部分的ではありますがSCMの手法とも言えます。
仕入れ先との間にはたくさんの交渉事がありますが、思惑通り解決できるかどうかはお互いの力関係や競合状況が大きく影響します。
とある企業の例ですが、社外の人間が出入りするエリアに「納期遅延の購買先ワースト10」が貼りだしてありました。
少々荒っぽいやり方だとは思いましたが、確かに仕入先にとっては緊張感を持たざるを得ません。
これは力関係で優位にあるからこそできることです。
なお、優れた仕入れ先に対しては表彰する等、鞭だけではなくちゃんとアメも用意していました。
逆に、力関係で優位に立てない仕入先に対してはあきらめて余裕をもった発注や在庫で対応している場合が多いようです。
まとめ
生産管理システム導入時においては仕入先や外注先も重要なステークホルダーですが社内統制の外にいるだけに統一したルールに乗せることも難しく、発注元のリーダーシップが要求されます。
またシステムでは解決できない課題も多く、交渉力も必要になるでしょう。
IT化に際してはバーコード等の自動認識やSCM等のデータ共有をうまく取り入れて省力化、効率化を目指しましょう。
筆者
プロフィール
星野拓 Takumi Hoshino
経歴:
自動車部品メーカーの設備技術者、物流システムメーカーのSEを経てトーテックアメニティに入社。
生産管理システムのプレSE及びプロジェクトマネージャとして豊富な導入実績を持つ。
第1種情報処理技術者
IoTエキスパート
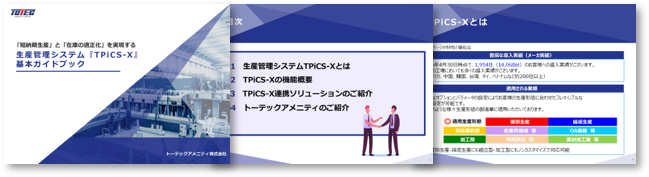
生産管理システム『TPiCS-X』
基本ガイドブック
お困りごとがありましたら、お気軽にお問合せください。